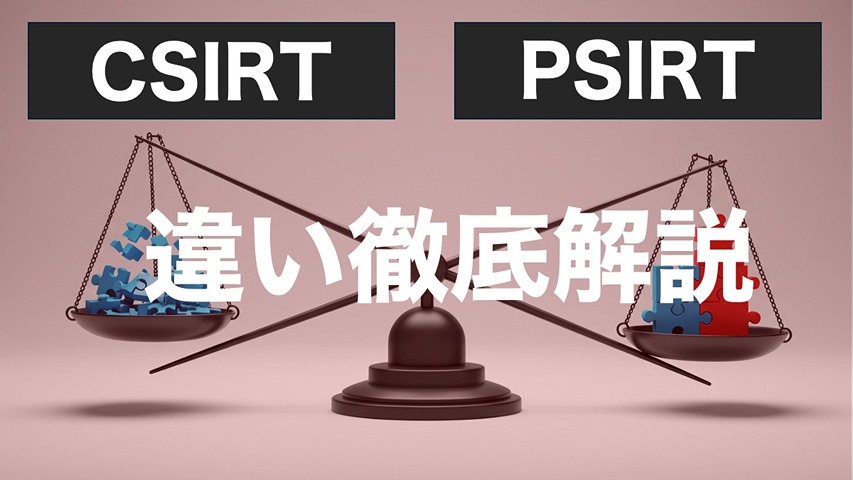なぜ今「サプライチェーン攻撃」対策が必須なのか?企業が取るべき実践策

- サプライチェーン攻撃
- ゼロトラスト
- セキュリティ対策
- SOC運用
- ログ監視
- ランサムウェア対策
~自社を守るために、まず“つながり”を見直そう~
「うちは標的にならない」と思っていませんか?
サイバー攻撃の潮流は今、「直接攻撃」から「間接攻撃」へと確実にシフトしています。
自社が大手企業や行政機関の取引先である限り、攻撃者にとって“踏み台”の候補になる可能性があります。サプライチェーン攻撃とは
サプライチェーン攻撃とは、取引先や委託先といった「信頼関係」を悪用して間接的に攻撃する手法です。
攻撃者は直接ターゲット企業に侵入するのではなく、セキュリティの甘い外部ベンダーや関連会社を突破口にします。
主な侵入経路は次の通りです。
- 外部ベンダーのアカウントを不正利用
- ソフトウェアのアップデートにマルウェアを混入
- 取引先企業のメールを装ったフィッシング
- クラウドストレージの共有設定を悪用
つまり、どんなに自社のセキュリティが強固でも、「つながる相手」が脆弱なら防御は成立しないというのが、この攻撃の本質です。
被害の実態と特徴
2020年の「SolarWinds事件」では、IT管理ソフトの更新ファイルに仕込まれたマルウェアが拡散し、米国政府機関を含む数千社が被害を受けました。
国内でも、取引先経由でランサムウェア感染や情報流出が発生する事例が増えています。
特徴的なのは次の2点です。
- 被害範囲が広い:1社の侵害が取引先・顧客に連鎖する
- 影響が長期化する:感染経路の特定や信用回復に時間がかかる
一度被害が発生すると、直接損失だけでなく取引停止やブランド毀損といった二次的リスクにも直結します。
セキュリティ担当者が直面する3つの課題
- 委託先・取引先のセキュリティ状況が見えない
取引が多層化し、すべての協力会社の対策状況を把握するのは困難。 - ゼロトラスト対応が追いついていない
クラウド利用やリモートワークが進み、「内部=安全」という前提が崩壊。 - 契約・ガバナンスの整備不足
契約書にセキュリティ条項が明記されておらず、責任分界点が不明確。
🛠️ 取るべき対策:3つの視点で考える
1. “つながり”の棚卸し
まずは、自社と外部がどのように接続しているのかを洗い出します。
- システム連携、VPN、ファイル共有、アカウント貸与などを可視化
- 業務委託先がアクセスできる範囲と権限を明確化
- 不要な接続・権限を削除
➡ 「誰が・どこに・どの範囲で」接続しているかを見える化することが第一歩です。
2. ゼロトラストモデルの導入
「信頼を前提にしない」設計思想を取り入れましょう。
代表的な施策は以下の通りです。
- 多要素認証(MFA)の強制
- ID管理基盤(例:Microsoft Entra ID)によるアクセス制御
- 条件付きアクセスでリスクベース認証
- Defender for Cloud Apps等による行動異常検知
➡ 接続元・行動内容に基づく継続的な検証を仕組みとして取り入れることがポイントです。
3. ログ統合と監視体制の強化
「侵入を完全に防ぐ」よりも「早期に検知し、被害を最小化する」考え方が重要です。
- 各製品・クラウドサービスのログを統合
- Microsoft SentinelなどのSIEMで横断的に分析
- SOC(Security Operation Center)と連携し、24時間監視体制を構築
➡ 異常なアクセスや不審な通信を早期に発見し、迅速に対応できる体制を整えることが鍵です。
被害を“防ぐ”だけでなく、“広げない”設計へ
侵入を完全にゼロにすることは不可能です。
だからこそ、「侵入されても被害を最小限に抑える」構成を目指しましょう。
- 権限の最小化
- 機密データの暗号化
- セグメント化によるネットワーク分離
- バックアップ体制の定期検証
これらにより、侵入後の横展開を防ぎ、被害を閉じ込めることが可能になります。
まとめ:信頼を前提にしない「関係性のセキュリティ」へ
サプライチェーン攻撃は、「信頼」を悪用する攻撃です。
しかし、取引関係を断つことはできません。
大切なのは、「信頼しつつも検証する」姿勢です。
- 外部接続の可視化
- ゼロトラストモデルの導入
- ログ統合による監視体制の強化
これらを段階的に進めることで、サプライチェーン全体のレジリエンス(回復力)を高めることができます。
Colorkrew Securityでは「ログ統合と監視体制の強化」で紹介したSIEMの導入や運用、そしてSOCまでまとめてご提供しています。是非お気軽にご相談ください。